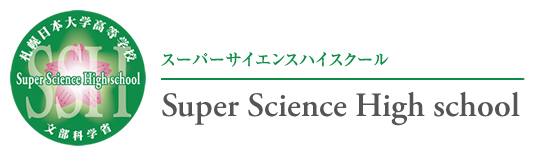2025.05.27
SSH(スーパーサイエンスハイスクール)は、創造性・独創性および科学的リテラシーを育み、未来を担う科学技術系人材を育成します。現在、本校ではSSHで培った学びを全校に広げています。夏休みに日本大学や各研究機関を訪れるなど、生徒たちの「科学する心」を刺激しながら、研究テーマを深めていく取り組みを行っています。
研究
テーマ
ネオジム磁石による地磁気の測定
●特進コース卒業(SSH)高田 駿さん
先輩たちから引き継ぎ、地球を取り囲んでいる磁場を測定する研究をしています。ネオジム磁石を糸につるし、その振動を計測する装置を手作りし、日本各地および世界の数か所で測定。1地点につき、100回振動する時間を10回計り、データを取りました。何度も失敗を重ねましたが、地球に働く磁場を正確に読み取ることができ、フィンランドで先輩が、シンガポールでは私が成果を発表。2019年12月の日本学生科学賞で、名誉ある旭化成賞をいただきました。SSHは1年次に研究の基礎を学び、2年次からは自分の興味のある分野の研究をはじめます。3年次は今までの研究の集大成として英語で発表を行います。段階的に学びを深める中で、先生方が発展的なことを教えてくれます。また、国際的にも刺激が受けられる素晴らしい環境です。