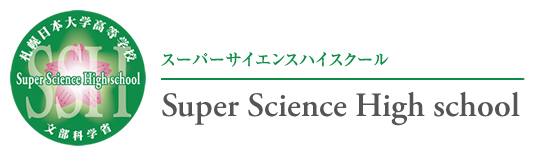2026.01.22
SSH(スーパーサイエンスハイスクール)は、創造性・独創性および科学的リテラシーを育み、未来を担う科学技術系人材を育成します。現在、本校ではSSHで培った学びを全校に広げています。夏休みに日本大学や各研究機関を訪れるなど、生徒たちの「科学する心」を刺激しながら、研究テーマを深めていく取り組みを行っています。
研究
テーマ
・ブラジルナッツ効果と浮力
・地磁気の鉛直成分の測定
●特進コース3年生(SSH)澤田 雄大さん
とにかく研究することが好きだったのでSSH指定校である本校に入学しました。私が在学中の研究テーマとしているのは【ブラジルナッツ効果と浮力】についてです。ブラジルナッツ効果というのは、大きさの異なる粉粒体の集合を袋などに入れてシェイクすると、最も大きな粒子が上層に浮き上がってくる現象のことです。さまざまな科学者の間でメカニズムが議論されていますし、さらに逆ブラジルナッツ効果と呼ばれる現象も起こり得る一筋縄ではいかない研究です。しかし自分が考えた理論が式として形になったり、仮説と合致した実験結果が出たり、また明確に研究の進展が見えた時の達成感は、何事にも代えがたいものがあります。個人研究の他にも科学部での活動、サイエンスツアーや研究者育成プログラムなどさまざまな学びがあり、SSHには科学に没頭できる環境が整っています。